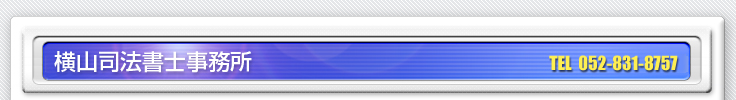こんにちは。愛知県名古屋市天白区の司法書士の横山和史です。
わたくしは,今年で独立開業して9年目になります。これまでに。たくさんの方から依頼を受け業務を
遂行してまいりました。
ひところ前は債務整理(破産申立書の作成,過払金返還請求など)の業務が多かったのですが,
最近は,ほとんど依頼がなくなりました。
代わって,相続関連の業務が増えてきました。
相続のご相談で特にご年配のみなさんに勘違いが多いのが,
①財産は長男が全部相続する。
②他家に嫁にでた女子には相続分がない。
③両親の面倒(特に介護)をみた相続人が全部財産を相続できる。
という考え方です。
まず,①の長男が単独相続するというのは昭和22年5月2日までに効力があった旧民法の家制度の考え方の影響だと思われます。
旧民法では,「家」を設け,血族を集中させました。家を統率するリーダーを「戸主」とよび,戸主は,大家族の生活保障をするかわりに,「家」の財産をすべて相続できるようになっていました。
こうした家制度を基本とした相続を「家督相続」といいます。
「家督相続制度」は,「人は平等である」という日本国憲法の精神に反することから,現在では廃止されています。
従いまして,長男だからと言って,相続財産を自動的に全部相続できるわけではありません。
②についても「家」制度の名残です。相続は「家」とは関係なく,血のつながりで発生しますので,「他家」へお嫁にいっても実父と実母の財産を相続する権利はなくなりません。
なお,似た事例で,養子となって他人の子供になった場合にも実の親との親子関係は消えないので相続ができます。(ただし,特別養子制度を除く)注意が必要です。
③「両親の面倒を見た者が財産をすべて相続できる」という規定は現在の民法にはありません。
寄与分といって相続財産の維持管理や亡くなった人への介護などで特別の貢献があった相続人に対して,相続財産を相続人全員の協議又は家庭裁判所の手続きで相続財産の取り分を増やす方法はありますが,遺産を全部相続できるわけではありません。
このように,「相続」は法定相続人が民法に決められているため,他に相続人がいる場合には,その方が,
相続人の欠格に該当する,廃除される,放棄する,他人へ譲渡しない限り,財産を全部相続することは難しいといえます。
特定の相続人(たとえば,長男,介護をした子供)に財産を多く相続させたい場合には遺言書を作成しなければなりません。ただし,遺言書で全部を長男に相続させると指定しても,ほかに相続人がいる場合には遺留分が発生する場合がありますので,遺留分を主張されると全部の財産の相続はできなくなります。
私が,実務相談で,相談者や依頼者のかたからのご意見で,民法を改正したほうが良いと思っているのは上記の③です。
家族は,何らかの個人的ないがみ合いや対立によって音信不通なることがあります。
その後,被相続人と疎遠になり,生活をともにしておらず,何ら介護や相続財産への維持管理などの貢献をしていない相続人にも血縁だけで,相続分が発生するのは,公平の観点から納得ができないという,被相続人の介護をされたご家族の気持ちはよく理解できます。
現行法では,遺言書で相続分を多めに相続させることはできます。
しかし,遺言書を作成せず,認知症や寝たきりになり,自分の財産管理ができない状態になってしまうと公証人立会いの遺言書であっても作成ができませんので,介護をしている方に多く相続させることはできません。
被相続人への介護をした方は,相続人として優先的に財産を相続できるように民法を改正すべきです。
介護は費用的にも肉体的にも精神的にも付き添った家族にとって大きな負担になります。
私は,何ら,被相続人の財産の維持増加に貢献していない相続人が,血のつながりだけを理由に相続できるのは公平に反すると考えます。
これから高齢化が一層進む日本社会のなかで,介護をしなければならない家族がいるご家庭でも安心して将来設計ができる制度に民法を改正すべきだと考えます。